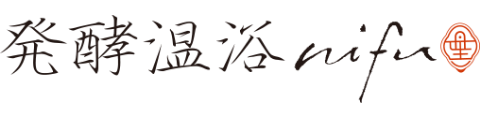医師にとってのエビデンス
医師は人々のヘルスリテラシーに役立つために、常に最新の医学情報を知っておく必要があります。ちなみに私は、世界的に権威があり医学界に影響力のある総合医学雑誌『The New England Journal of Medicine 』等を購読しています。このジャーナルには、新たな研究論文だけでなく、既にある学説を再検証した論文も登場します。膨大な数の被験者によるデータは、エビデンスとして信用に値します。
このような、科学的根拠に基づき医療を進める方法とは別に、患者の人生や価値観、疾患の捉え方などに重点を置くナラティブ・メディスン(Narrative Based Medicine)を重視する医師もいます。これもそれなりに意味はありますが、医師の経験値がエビデンスでは不安も残ります。
また、TVなどのメディアに登場する医師には、エビデンスより企画の方向性に合わせて発言していると感じる人もいるし、同じ医師として「そんな無責任なことを言っていいのか」と思うことも多々あります。自身のヘルスリテラシーを高めるための精査、それは“情報を鵜呑みにしない”という、情報過多社会においての常識でもあります。
口にするものは、その背景に関心を持つ
日本には“牛乳を飲むと健康になる”と思う人がいますが、欧米では様々な理由で牛乳や乳製品を摂らない人がいます。近年、ベジタリアン人口が世界規模で増え続けている背景には、ヘルスリテラシーの高い人が、ディスクロージャー(企業が、経営内容などの情報を株主や投資家、債権者などに開示すること)にも注意して、食環境を改めているからでしょう。
私は牛乳を飲まないもののチーズは食べたくなるので、チーズは“たまに食べるご褒美”程度に抑えています。衛生や健康を気にし過ぎると、「健康不安」「病気不安症」など精神疾患になりかねません。そして特定のことにこだわり続けると、偏りや先入観、偏見といったバイアスがかかり過ぎることもあるので注意しましょう。
ビタミン剤のようなサプリメントや機能性食品は、欠乏した栄養素を補うためのものです。基本的に、正しい食生活を送る健康な人にサプリメントは不要です。ただ、たとえば同じトマトでも、露地栽培とハウス栽培では栄養価が違うという話もあるので、食材の栄養価を補うためにサプリを飲む、という考え方もあるでしょう。
サプリメント選びには、製造元や品質に対する注意が必要です。医薬品を製造・販売していないのに○○製薬と名乗る企業もあります。これらが全て悪いわけではありませんが、商品に対する責任を問えるのでしょうか。また、日本で認可されていても、欧米では発がん性などのリスクがあるという理由で禁止されている成分もあります。一般の方々がそこまで専門的に追求することは難しくとも、関心を持つことは大切です。
メディアで紹介される健康法も、気候や生活環境が多彩な日本では一概に効果があるとは限りません。海外のダイエット法も、人種が違えば結果も変わるでしょう。エビデンスを明記した情報でも、そのエビデンスが又聞きや拡散された情報の再加工など、出所不明な場合が多くあります。見聞きした健康情報をすぐ取り入れるのではなく、多角的に精査をする意識を持ちましょう。
健康に積極的なアプローチが現代風
厚生労働省が推奨する「日本人の食事摂取基準」は、健康のために摂るべき栄養素の基準値を、“○○を1日○mg”というように、それを満たさないと健康を害する可能性があるという、必要最低限の量を示しています。
医学会ではオプティマルドーズ(Optimal Dose 適切な用量)が推奨されていますが、近年は、たとえばビタミンCを点滴などで最低限以上を摂ることで効果が実証されています。もちろん個人差はありますが、このような積極的な対処法も評価され始めているのです。
nifuの発酵温浴も積極的な対処法といえるでしょう。冷えた体で血行が悪くなっていても、ある程度までは普通に生活できます。でも、発酵温浴で定期的に深部体温を上げる習慣は、理想的な健康状態をキープするためのアクションを実践していることになります。体温を上げる温浴は、医学が未発達だった時代から続く養生の基本です。これはエビデンスが曖昧なサプリを沢山飲むよりもヘルスリテラシーが高い健康法だといえます。医学的根拠に基づいているなら、積極的なアプローチにトライしてもいい。それがnifuの発酵温浴のように日常生活の“癒しのひととき”にもなるなら尚良しですね。