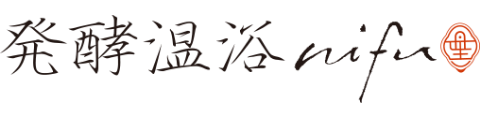機能性食品の発展や画期的なワークアウトなど、80年代から盛んな日本の健康ブームは今も続いています。近年の日本は、社会保障給付費が国家予算の多くを占め、その中でも医療費が突出していることから、国民一人ひとりの健康管理の質を高めて医療費を減らすことは、国の施策としても重要視されています。
しかしなぜ、数十年も健康ブームが続いているのに医療費が増え続けているのか。それは、国民の「ヘルスリテラシー」が低いことも原因の一つなのではないでしょうか。
ヘルスリテラシーとは、「健康に関する様々な情報を入手し、理解し、活用する能力」を指します。この「健康に関する様々な情報」は多岐に渡るため、今回はトピックスに分けてお話しします。
健康保険に頼りがちな日本人
日本は国民の健康保険加入が義務付けられ、健康保険被保険者証1枚でどんな医療機関にもフリーアクセスできる国です。そして「病気になっても病院に行けば大丈夫」と、不摂生を続けてしまう人も多くいます。しかしこの考え方は、自分の人生に影響するヘルスリテラシーを、人任せにしているように感じます。
日本の医療現場は、専門医制度が主流になりつつあります。各診療科の専門医が、質の高い医療を提供するようになりました。たとえば、私の専門には、膠原病の一種であるシェーグレン症候群やドライマウスなどがありますが、もし自分の不調がこれらの症状に似ているかもしれないと思ったら、まず情報収集を始めませんか? つまり今の時代は「具合が悪いから近くの病院に行く」というような大雑把なものではなく、自分の症状に詳しい専門医を探すことが望ましいのです。もちろん、病院に行かずとも市販薬で症状が改善することもあります。だからこそ、日頃からセルフチェック、セルフケア、セルフメディケーションを心掛けることは、ヘルスリテラシーを高めることへの第一歩です。
日本のように全国民をカバーする公的医療保険制度がないアメリカでは、国民は民間の保険会社に頼るしかありません。病気をすれば保険料も上がるため、貧富の差で受けられる医療に格差が生じています。これを改善する米医療保険制度“オバマケア”(2010年)も施行されましたが、十分に機能していません。そこでアメリカでは、国民にヘルスリテラシーを啓蒙する組織の活動や、米国疾患予防管理センターが開発したe-leaningプログラムの無料公開など、国家全体のヘルスリテラシー向上が積極的に行われています。
自分が飲む薬の「作用」を知る
アメリカに比べ、日本は簡単に診療を受けられる点で恵まれていますが、日本人の薬の服用量は、欧米の約40倍といわれています。処方箋で薬を買えば市販薬より安いし、薬を出したがる医師も、薬をもらいたがる患者さんも多いようです。そのため日本では、「ポリファーマシー(Poly+Pharmacyの造語)」が社会的な問題になっています。
ポリファーマシーとは、複数の薬の服用で副作用などのリスクが高まる状態です。あちこちの病院でそれぞれに薬を処方された人が、相互作用を確認せずに薬を飲み合わせることで起こります。でももし医師が「大丈夫ですよ、たくさん食べてしっかり寝れば治ります」と薬を処方しなかったら、「薬も出してくれないなんて、なんて冷たい医者なんだ」と思う人は多いのではありませんか?
薬は化学物質ですから、飲み方や併用を間違えれば「毒」にもなり得ます。医師もポリファーマシーを注意して処方を検討しますが、自分でも処方された薬の作用を理解して多剤併用しないことは大切です。基本的に、病気を治してくれるのは、自分の体力、免疫力です。
たとえば風邪の処方にすぐ抗生物質を出す医師もいるので、「風邪は抗生物質で治る」と思っている人も多くいますが、風邪のようなウイルス感染に抗生物質は効きません。風邪による炎症や、炎症が波及して肺に潜在する細菌が増えることを抑える時に、抗生物質が有効だとされています。痰や鼻水が出たりする細菌感染の兆候があった時に抗生物質を飲む、という理解が正解です。
また、長引く発熱症状にアセトアミノフェン(解熱鎮痛成分)が処方されるのは、熱発が長く続くと脳に影響が出るからです。脳の健康を保つための処方であり、熱が下がってもウイルスを撃退したわけではありません。風邪で処方された薬の作用を理解して適切に服用し、回復まで安静にしている人がヘルスリテラシーの高い人であるといえます。
ちなみに日本では、感染症で抗生物質を多用した人に従来の抗生物質が効かなくなったという話もありますが、アメリカでは、検査の結果その効果が疑わしいという理由で、そもそも抗生物質を処方しない医師も多いそうです。抗生物質に限らず、日本の人口はアメリカの半分くらいなのにアメリカの何十倍も薬が売れるといわれています。日本は保険制度の三割負担で薬を安く買えることに加え、「薬を飲めば治る」と安易に考える国民のヘルスリテラシーの低さが否めません。
食に溢れる社会で「何をどう食べるか」
私たちの身体は食べ物から出来ていて、体力や免疫力を高めることで健康を維持しています。たとえば、私たちの先祖は、生命維持に重要な「糖」が少ない時代も生きながらえてきました。でも逆に、現代社会は糖が溢れています。本来、少ない糖で維持できる体に過剰な糖を摂り続ければ、当然病気になりますよね。これまで中高年の生活習慣病とされてきた糖尿病は、今や若年層の間でも増えています。
巷に溢れるファストフードのメニューには、パン、麺、米飯が多くありますが、これらの主成分である炭水化物は、体内で糖に変わり血糖値を上げます。血糖値の上昇を抑えるためにすい臓からインスリンが分泌されますが、ファストフードで炭水化物ばかり食べていると、すい臓が疲弊して正常に機能しなくなり、血糖値が下がらず糖尿病を発症します。
今の日本は、糖尿病患者が一千万人、糖尿病予備軍も一千万人いるとか。糖尿病になると、糖尿病性網膜症や感染症など色々な病気も併発します。ですから、炭水化物主体のファストフードを食べるなら、最初にサラダで食物繊維を摂り、後から食べる炭水化物(糖)の吸収を緩やかにする・・そういう意識を持って食事をすることが大切です。
習慣を見直す。伝統を振り返る。
歯磨き不足や喫煙などの生活習慣がリスクを高める歯周病も、若年層に増えています。近年は歯周病が糖尿病に悪影響を及ぼすことがわかったため、日本糖尿病学会の下部組織である糖尿病協会では、糖尿病専門医だけでなく、歯科医師や栄養士も連携して対処するようになってきました。しかし、糖尿病や歯周病のような生活習慣病は、自分で食を選ぶ年齢から栄養学や健康知識を身につけておけば避けられるはずです。学校の必修科目にこのような教科がないのは残念ですね。
新たな情報だけでなく、我々日本人がどのような食生活を経てきたかを振り返ることも、ヘルスリテラシーに役立ちます。
昔、「長寿県」といえば沖縄県が1位の常連でしたが、2000年頃から沖縄県の順位が後退しています。この原因には、沖縄に脂質や炭水化物が多いアメリカの食文化が浸透したことや、生活習慣病の放置などが挙げられています。近年の長寿県上位は、滋賀県や長野県など。アメリカの合理的な食文化よりも、先人の知恵が詰まった伝統食が根強く残っているからではないでしょうか。科学的に裏打ちされたリテラシーが無くとも、地域で受け継がれてきた伝統食には、その地で長生きするための“健康のヒント”があると思います。
日本の懐石料理の“食べ方”も、昨今流行りの「ベジファースト」「カーボラスト(炭水化物を最後に食べる食事法)」に通じます。懐石料理は、先付けや八寸などの野菜料理で始まり、食事の最後は米飯です。最初に食物繊維を摂り最後に炭水化物を摂るという食べ方は、先にもお話しした通り、血糖値の急激な上昇を抑える食べる順番です。
ヘルスリテラシーの結果、身体という「器」の準備
科学や医療は進化しますから、人生が続く間はヘルスリテラシーのアップデートが必要です。見聞きした健康に関する情報を精査する習慣が身につけば、薬の知識も増え、広告の過剰な宣伝文句に惑わされることも減るでしょう。「自然派」「高機能」「○万人が愛用」など、世の中にはエビデンスが曖昧な商品がたくさんあります。
そして、昔から「頭寒足熱」という言葉があるように、身体を温めることは、科学や医学の進歩に関わらず普遍の健康法です。古代ローマ帝国時代はヨーロッパ各地で傷病者の温泉療法が盛んでした。日本の『古事記』や『日本書紀』にも温泉で身体を癒したという記述があります。入浴で身体の深部体温を上げることは、人類の経験値、経験則に基づく健康法なのです。nifuの発酵温浴のように、短時間の入浴で、乳酸菌豊かなヒノキのおがくずでスキンケアも期待できる深部体温の上げ方は、古来健康法の最新アップデート版といえます。